
ユンボ
2025/05/21
3,749
建設機械の脱炭素化! 電動バックホウを導入するメリット・導入の注意点
本記事では、建設機械のカーボンニュートラルへの取り組みから、各メーカーの最新動向について詳しく解説します。また、GX建設機械認定制度やレンタル料金についても説明しています。
この記事でわかること
- 電動バックホーとは
- 電動バックホーの性能
- 電動バックホーを導入するメリット
- 電動バックホーの市場動向
建設機械でも進むカーボンニュートラルへの取り組み
建設業界は、日本全体のCO2排出量の約1.4%を占めています。政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、建設現場でも環境への負荷を減らす動きが急速に進んでいます。
特に、2030年度までに2013年度比でCO2を40%削減するという目標が設定されており、それに向けて次のような取り組みが進められています
- 省燃費運転の推進
- バイオ燃料や水素などの新しい燃料の導入
- 環境性能の高い最新の建設機械の活用
電動機械には、CO2の削減以外にも以下のようなメリットがあります
- 作業時の騒音や振動が少ない
- 燃料コストが安い
- メンテナンス費用が削減できる
- LED照明の使用
- 太陽光パネルなどの再生可能エネルギーの導入
- 作業の効率化やエネルギー使用の「見える化」

脱炭素へ進む!建設機械メーカーの電動化への取り組み
主要メーカーの取り組み
- コマツは、電動建機7機種すべてで「GX建設機械認定」を取得。2023年度を“電動建機元年”と位置づけ、積極的に市場へ投入しています。
- 日立建機は、バッテリー駆動ショベル「ZE85」を皮切りに、2トン〜13トンクラスまでラインナップを拡大。
市場も拡大中
技術開発も活発に
- ホンダは交換式バッテリーを共同開発し、小型機への導入を進め中。
- 日立建機は可搬式の急速充電設備を開発し、建機とのセット販売を計画。
- コベルコ建機は、水素燃料電池の技術を活かし、長時間の連続稼働を実現。
2023年にスタート「GX建設機械認定制度」とは
建設機械の稼働によるCO2排出量は国内産業部門の約1.4%を占めており、その削減は建設業界における重要課題となっています。国土交通省はこの課題に対応するため、電動建機の普及促進に向けた認定制度を確立しました。
認定対象は、バッテリー式または有線式の電動ショベルとホイールローダー、ホイールクレーンです。2023年12月の初回認定では4社15型式の電動ショベルが基準を満たしました。
認定機械には国土交通省の認定ラベルが付与され、複数の優遇措置が適用されます。環境省による購入費用の補助は従来型との差額の3分の2、充電設備導入費用は価格の2分の1が支給されます。さらに、公共工事での優遇措置も検討されています。
GX建機認定制度の導入により、建設機械メーカー各社の電動化開発は新たな段階に入ったと言えます。コマツは7機種、竹内製作所は4機種、コベルコ建機は3機種など、各社が製品開発を強化しています。
電動バックホーの先駆けはコマツ
1921年に創業したコマツは、建設機械分野で世界をリードする企業として100年以上の歴史を築いてきました。特に油圧ショベルやブルドーザーの分野では、世界市場シェアの上位を維持し続けています。
コマツは2023年度を電動化建機の市場導入元年と位置づけ、マイクロショベルのPC01E-2から20トンクラスのPC200LCE-11まで製品の種類を増やしました。特に3トンクラスのPC30E-6は、都市部での需要に応える製品として注目を集めています。
コマツはホンダとの協業により着脱式バッテリーシステムを開発し、小型機で実用化しました。中型機向けには、プロテラ社と共同でリチウムイオンバッテリーの開発を進めており、有線式とバッテリー式の両方のラインナップで多様な現場のニーズに対応しています。
電動建機市場におけるコマツの先進的な開発は、業界全体の技術革新を牽引しています。
世界初のハイブリッド油圧ショベルである「PC200-8E0」
「コマツ・ハイブリッド・システム」と呼ばれる独自技術は、旋回電気モーター、発電機モーター、キャパシター、ディーゼルエンジンを組み合わせた革新的な仕組みになっています。車体旋回の減速時に生じるエネルギーを電気に変換して蓄電し、エンジン加速時の補助動力として活用する画期的なシステムです。
従来機「PC200-8」と比較して平均25%の燃費削減を達成し、特に旋回作業が多い現場では最大41%の低減効果を記録しました。エンジンを低速回転域で使用可能としたことで、待機時の燃料消費も大幅に改善しています。
PC200-8E0は建設機械業界に大きな影響を与え、環境対応における新たな基準を確立し、各メーカーのハイブリッド建機開発を促進するきっかけとなりました。2009年には中国・北米市場へも展開して、世界規模での環境技術革新を牽引しています。
このモデルにより、建設機械業界全体で環境負荷低減技術の開発が加速し、現代の電動化技術の基盤ができました。
電動バックホーのレンタル料金
- 1トンクラス:日額8,000円
- 2トンクラス:日額9,000円
- 3トンクラス:日額9,000円
電動バックホーを導入する5つのメリット
特に注目すべき5つのメリットを紹介します。
排気ガスがゼロ
低振動・低騒音
メンテナンスコストの低減
低コストで運用可能
作業精度が向上
電動バックホーを導入を検討する際の注意点
- 作業内容と適合性の確認
電動バックホーは、都市部や屋内作業など騒音や排気ガスを抑える必要がある環境に適していますが、大型の土木工事や長時間の稼働が必要な場合は能力不足になる可能性があります。大規模工事や馬力が求められる作業では、機種によっては性能不足になる可能性があるので注意が必要です。 - 地形や気象条件
電動バックホウのバッテリーに採用されているリチウムイオン電池は、温度低下に弱いため、寒冷地や低気温下では性能低下の影響を受ける可能性があります。そのため、導入時は、使用環境などを考慮するとともに適切な運用温度範囲を確認してください。 - 稼働時間とバッテリーの充電時間
一度の充電でどれだけ作業できるか(稼働時間)と、充電にかかる時間を比較検討する必要があります。予備バッテリーの用意や充電設備の確保も重要です。 - 充電インフラの整備
電動仕様機の導入には充電設備(配電盤)および配線が必要です。特に山間部の工事などではバッテリー充電用の発電機が必要です。電動バックホーの導入前には充電設備の設置場所や電力供給能力を事前に確認し、作業現場でスムーズに充電できる体制を整える必要があります。 - ランニングコストが高額になりがち
電動モデルは一般的に従来のディーゼルモデルよりも高価です。補助金や税制優遇制度が利用できる場合は積極的に活用しましょう。また、導入時は予備バッテリーや充電するための設備面など本体価格以外のコストも考慮しなければばりません。
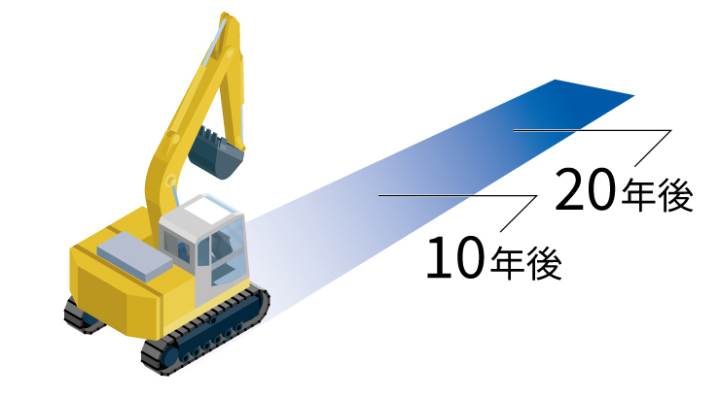
電動バックホー・電動建機市場における今後の動向
過去を振り返ると、2000年代後半からハイブリッド式油圧ショベルが市場に登場し、その後、完全電動化への期待が高まりました。現在では、各建機メーカーがミニバックホーの電動化に注力しており、3〜8トン級の電動ミニバックホーが2021年以降続々と市場に投入されています。
しかし、大型バックホーの電動化には、バッテリーのコストや稼働時間、充電性能などの課題が残っており、実用化には時間がかかると予想されています。今後、リチウムイオン電池の技術進展により、バッテリーの大容量化・小型化が進めば、電動バックホーの市場はさらに拡大する予想です。
排ガス規制や騒音に配慮された電動建機は、大気汚染や騒音が問題視される都市部の建設現場を中心に需要が増加しています。特にヨーロッパや北米では、建設業界における厳しい環境規制が導入されており、これに適合する電動バックホーやミニショベルなどの開発が加速しています。一方、アジア市場でも急速な都市化に伴い、電動建機への関心が高まっている状況です。
昨今における重機市場の主要なトレンドとしては、「環境意識の向上」、「エコフレンドリーな製品の需要増加」、「省エネ技術の進歩」、「都市化の進展」、そして「自動化の導入」が挙げられます。これらの要因が相まって、電動バックホーの市場は今後も成長が見込まれるでしょう。
まとめ
特に都市部での建設プロジェクトにおいて、電動バックホーの需要は高く、リチウムイオンバッテリーの開発に伴い新型機種も開発されていく予想です。各メーカーの技術開発競争により、性能向上とコスト低減も進むでしょう。



 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


