
高所作業車
2025/05/19
3,174
高所作業とは? 必要になる資格や高所作業のシチュエーションを解説
労働安全衛生法では高さが2m以上で作業を行う場合、作業床と手摺などの囲いを設けて墜落を防止することを原則としています。つまり、高所作業は高さ2m以上の箇所で行う作業ということです。
また、厚生労働省が発表している労働災害状況を見ると、建設業界の死亡事故で1番の割合を占めているのが墜落・転落災害です。
ゆえに、労働安全衛生法では高所作業に関する法律が多く定められており、建設業界で働く人々は高所作業について学ばなければなりません。
この記事では現場監督者の経験者より話を伺い、どこよりも詳しくお伝えします。
- 高所作業とは何か
- 高所作業の危険性
- 高所作業で必要になる資格
高所作業の安全について理解を深めておかなければならない、新人現場監督の方にこそ、読んでもらいたい内容となっています。ぜひ、最後までお読みください!
高所作業とは?
つまり、2m以上の箇所から墜落すると命の危険があるということ。これが、高所作業は2m以上からと認識されている理由です。
実際に、芸能人が番組収録中に2mの位置から転落し、全治6週間の大怪我をしたという報道もあります。
このように、人は2m以上の箇所からの墜落でも命の危険があるため、労働安全衛生規則で定められているのです。
2m以上と言われても、想像しづらいかもしれません。その場合は、街中でよく見かける自動販売機をイメージしてください。自動販売機は約2mの高さになります。
事業者って何?
死亡事故で1番の割合を占めているのが墜落・転落災害
厚生労働省が発表している「平成30年 労働災害発生状況」を参照すると、909件の死亡災害が発生しています。その中でも墜落・転落災害による死亡事故は、256件。およそ28%の割合を占めています。約4人に1人は、墜落・転落災害で死亡しているのです。
2番目に割合を占めているのが、交通事故で約19%になります。墜落・転落災害と交通事故で半数を占めているため、現場では墜落・転落災害を防止することがもっとも大切というわけです。
このあとの章では、高所作業のシチュエーションや資格、墜落・転落災害の実例を紹介します。建設現場で働いている方は自分の命を守るためにも記事を最後まで読み、理解を深めることをおすすめします!
墜落と転落の違いって何?
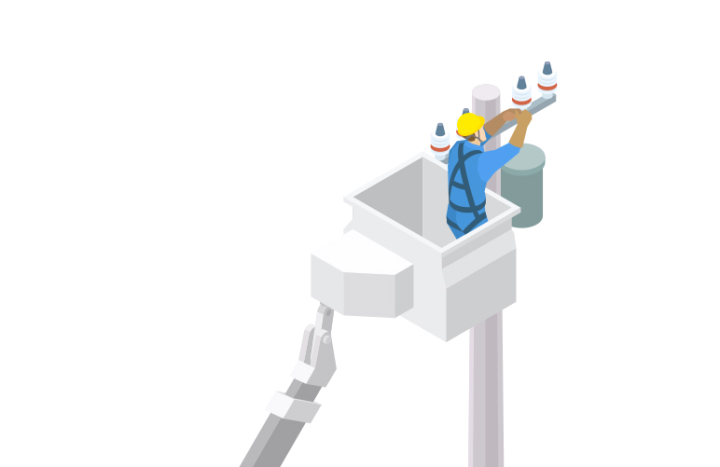
よくある高所作業のシチュエーション3選
シチュエーション1:高所作業車での作業
高所作業車の定義には「作業床を2m以上の高さに上昇させられる」という決まりが含まれています。つまり、高所作業車を使用した場合は高所作業になるということです。
高所作業車は、人の手が届かない場所でなおかつ、足場を組み立てるのが困難な場合に使用されます。また、垂直式高所作業車という種類も存在しており、狭い箇所で大いに活躍してくれる高所作業車です。
高所作業車でよく起きる墜落災害は、以下の通りです。
- 高所作業車のバランスが崩れ、転倒してしまう
- 高所作業車から身を乗り出したために、墜落してしまう
- 作業床で重量物を持った際にバランスを崩し、墜落してしまう
シチュエーション2:屋根や山留材の上での作業
山留材に関しては、立坑が深くなればなるほど墜落時の危険性が高まります。現場にもよりますが、山留材から地面までが6m以上になる場合もあり、 墜落した場合はひとたまりもありません。
屋根の補修作業に関しては、足元の確認を怠ってしまい、足を踏み外すことによる転落災害がもっとも発生しやすいです。建物が古くなっていると屋根がボロボロになっていることもあり、踏み抜いてしまうことも考えられます。
屋根や山留材の上では、常に危険と隣り合わせであることを忘れないでください。事業者の方は、親綱などの安全措置を十分に行う必要があります。
シチュエーション3:高層ビルの窓清掃や設備点検作業
もちろん、普段から高層ビルで作業をしているプロの方が行いますが、それでも災害が起きてしまうのが高所作業の恐ろしさです。建設現場でも高所作業は鳶工の人が行うのが一般的です。しかし、慣れているプロだからといって安全を怠らないように意識してください。
高層ビルの窓清掃や設備点検は、専用のゴンドラに乗って行います。ゴンドラに何かしらの衝撃がおきて墜落してしまうケースがよくある災害事例です。

高所作業をする際に取得しておくべき3つの資格
今回解説する資格は、以下の通りです。
- フルハーネス特別教育
- ロープ高所作業特別教育
- 高所作業車技能講習
1つ注意点として、絶対に無資格の状態で作業をしてはなりません。受講時間や費用に関しても記載しますので、参考にしてください。
資格1:フルハーネス特別教育
- 胴ベルト型
- フルハーネス型
しかし、胴ベルト型には欠点が存在します。それは、宙吊りになった際の腹周りの圧迫や耐久性に関しての不安です。これらの問題を解決するために、フルハーネス型の墜落制止用器具が開発されました。
フルハーネス型は体全体を覆うように何本ものベルトを巻くため、安全性が優れています。
また、墜落した場合も胴ベルト型に比べて安定した状態で宙づりになるため、圧迫感をあまり感じません。
労働安全衛生規則519条では「作業床を設けるのが困難な場合や囲い、手すりを取り外す際には労働者に墜落制止用器具を使用させる等、墜落による危険を防止する措置を講じなければならない」と定められています。
建設現場では、足場の一部を取り外して作業を行う場合が多々あります。その際には、必ず墜落制止用器具を使用しなければなりません。
また、墜落制止用器具はフルハーネス型を使用することが原則になっていますが、胴ベルト型を使用できる条件があります。その条件とは、以下の通りです。
- 作業箇所の高さが6.75m以下
- フルハーネス型では地面に到達してしまう場合
フルハーネス特別教育は学科が4.5時間。実技が1.5時間の計6時間で取得可能です。受講する機関によりますが、費用は1万円前後になります。
まだフルハーネス特別教育の資格を取得していない方は、近くの労働基準協会のHPを検索してみてください。
安全帯の規格が変更。 正式名称を墜落制止用器具へ
呼び方だけではなく、性能要求など規格の見直しも行われ、平成31年2月1日から「墜落制止用器具の規格」が適用されました。ゆえに、「安全帯の規格」と記載されている胴ベルトやフルハーネスを使用していると法令違反になります。
実際に、胴ベルトやフルハーネスを使用している方は1度確認してみてください。
資格2:ロープ高所作業特別教育
のり面とは、人工的な手を加えられて作られた斜面のことを指します。斜面では足場などの作業床を組み立てることができません。ですので、ロープを使用することが一般的です。
ロープ高所作業特別教育では、ロープについての正しい知識を身に付け、転落災害の防止を目的としています。
頻繁に使用する資格ではないため、該当する作業を行う場合に資格を取得するのがおすすめです。学科が4時間と実技が3時間の計7時間でロープ高所作業特別教育は取得できます。費用に関しても、1万円前後で受講可能です。
資格3:高所作業車技能講習
高所作業車の資格は2種類あります。
- 高所作業車技能講習
- 高所作業車特別教育
どちらの資格を取得しようか悩んでいる方は、すべての高所作業車を操作できるようになる技能講習の取得をおすすめします。
高所作業車技能講習は、学科が10時間と実技が6時間の計16時間で取得可能です。特別教育と違い、取得までに2〜3日かかります。こちらも受講する機関によりますが、費用は4万円前後です。
高所作業車使用時に起きやすい墜落災害とは?
高所作業車の転倒による墜落災害
高所作業車が転倒すれば作業床で作業をしている人が大変危険です。事前に敷鉄板を敷設するなど対策を講じるようにしてください。
身を乗り出して作業してしまう
実際に、現場で過去の災害事例などを目にする機会がありますが、高所作業車での墜落災害は身を乗り出して作業していたため、発生してしまうことがわかります。
高所作業車では墜落制止用器具を必ず使用して、作業床を作業位置までこまめに操作するようにしてください。
重量物を持ち、バランスを崩してしまう
皆さんも普段の生活で重量物を持った際に、足元がふらついた経験があるのではないでしょうか? 1度バランスを崩すと、高所作業車では重大災害に繋がることを忘れてはいけません。
どうしても重量物を持つ必要がある場合は、墜落制止用器具がしっかりと機能しているかどうか確認してください。確認後、体勢を整えて作業を開始することをおすすめします。
まとめ|今からでも遅くない! 高所作業について理解をふかめよう
今回ポイントを改めてまとめると、以下の通りです。
- 高所作業は2m以上での作業のこと
- 墜落・転落災害は死亡事故の1番の原因である
- 高所作業に関する資格の中で、フルハーネス特別教育がもっとも大切になる



 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


