
ユンボ
2024/11/21
11,929
クレーン機能付きバックホウとは?必要な資格やレンタルのメリットについて解説!
クレーン機能付きバックホウ
建設機械の多機能化が進む中で、現在のバックホウは、アーム、バケットを利用したクレーン機能搭載の機種がメジャーです。1台で2荷役の作業ができるクレーン機能付きバックホウは、その利便性から多くの作業現場で普及しています。
しかし、クレーン機能付きバックホウで作業するにはクレーンの資格も合わせて保有していなければなりません。
本記事では、クレーン機能付きバックホウや操作に必要な資格、レンタルのメリットについてご紹介します。
【この記事でわかること】
・クレーン機能付きバックホウに必要な資格
・クレーン機能付きバックホウとは
・クレーン機能付きバックホウをオペレーター付きでレンタルするメリット
クレーン機能付きバックホウは目的に あった資格が必要
クレーン機能付きバックホウは、法令上では移動式クレーンとして認められています。
そのため、クレーン機能を使用して作業を行うには、次のような資格が必要です。
・移動式クレーン運転士免許
・小型移動式クレーン運転技能講習(5t未満)
・移動式クレーン運転の業務に係る特別教育(1t未満)
・玉掛け特別教育(1t以上)
・玉掛け技能講習(1t未満)
ただし、これらすべての資格が必要というわけではなく、操作するクレーン機能付きバックホウの吊り上げ荷重に適した資格を取得することで作業が可能です。
また、車両系建設機械を掘削作業などの用途で作業を行う場合は、その用途・機体質量に応じて、「車両系建設機械運転技能講習修了者」または、「車両系建設機械の運転の業務に関する安全のための特別教育」を受講しなければなりません。
クレーン操作を行う場合は、玉掛けの資格は不要ですが、建設現場での需要が高いため取得しておくことを推奨します。
移動式クレーン運転士免許
・内容: 学科試験・実技試験
・費用: 約13万円
・期間: 4~6日間
通常、クレーン機能付きバックホウの吊り上げ荷重は5t未満で開発されています。そのため、今後さらに大型のクレーンを操作する予定がない場合は、次の「小型移動式クレーン運転技能講習」を検討すると良いでしょう。
2024年11月 トクワールド調べ
小型移動式クレーン運転技能講習
多くの現場で利用される「0.45m3クラス」や「0.7m3クラス」のクレーン機能付きバックホウは、吊り上げ荷重が1.5〜3t程度となっています。そのため、この講習を受講することで、クレーン機能付きバックホウの操作が可能となります。
・内容: 学科試験・実技試験
・費用: 約3万円
・期間: 2~3日間
この講習は試験合格が不要で、講習を受講すれば技能講習修了証が発行されます。費用と講習期間が少なく、短時間で資格を取得したい方におすすめです。
2024年11月 トクワールド調べ
移動式クレーン運転の業務に係る特別教育
「0.2m3クラス」のクレーン機能付きバックホウの吊り上げ荷重は1t未満が一般的です。そのため、この特別教育を受講すれば操作が可能です。
・内容: 学科試験・実技試験
・費用: 約2万円
・期間: 2日間
小規模な現場工事を担当する方にはこの資格が推奨されますが、1t未満の荷重では大規模な現場では物足りない場合があります。
2024年11月 トクワールド調べ
玉掛け特別教育
・内容: 学科試験・実技試験
・費用: 約2万円
・期間: 2日間
他に玉掛け作業員がいる場合は、この資格が不要になることもありますが、現場でのスキル向上のため取得しておくことをおすすめします。
2024年11月 トクワールド調べ
玉掛け技能講習
・内容: 学科試験・実技試験
・費用: 約3万円
・期間: 2~3日間
クレーン操作に必要な資格を取得する際には、特別教育よりも「玉掛け技能講習」を選択することをお勧めします。
2024年11月 トクワールド調べ
そもそもクレーン機能付きバックホウとは?
本来、バックホウは地面を掘削するための機械であり、荷を吊るなどのクレーン作業は「用途外」の使用です。
しかし、インフラの普及に伴い、上下水道や電気・ガスの工事現場では、物をつり上げる作業が頻繁に必要とされ、そのたびに移動式クレーンを使うのは不効率でした。その結果、現場での、事故が多発したことを受け、1992年(平成4年)に「労働安全衛生規則第164条」が改正されます。
改正後は、特定の条件下で安全措置を講じれば、車両系建設機械でのつり上げ作業が認められるようになりました。つまり、規格を満たしたクレーン機能付きバックホウであれば、吊り荷作業を行うことができるのです。
昨今出回っているバックホウの殆どが、クレーン機能付きの機種といっても過言ではなく、1台で「掘る・吊る・埋める」の3つの機能を実現できる機械として需要があります。
また、管の埋設工事、上下水道の整備、道路工事における側溝の設置、河川工事など、多様な現場での吊り作業で活躍します。
【クレーン機能付きバックホウの主な特徴】
・荷を吊り上げ、運搬を行うことができる。
・振れや転倒を防止する安全対策が施されている。
規格を満たした移動式クレーン
作業装置であるアームやバケットには、特定の要件を満たす吊り上げ用具が取り付けられています。
クレーン機能付きバックホウはオペレーター付きレンタルがおすすめ
また、車両系建設機械(バックホウ)の資格は持っているけど、クレーンの資格が未取得状態である場合は、せっかくのクレーン機能も無駄になります。そのような場合でもオペレーター付きの重機レンタルがおすすめです。
【オペレーター付きの重機レンタルはこんな方におすすめ】
・庭石の撤去作業がしたいが、塀や電線の上からしかバックホウで庭石が吊れない。
・クレーン機能付きバックホウを使いたいが資格未取得のため操作ができない。
・資格はあるがバックホウやクレーン機能の操作に慣れていない。
重機をオペレーター付きでレンタルするメリット
また、運転者は、クレーン作業を行う際には通常のショベル作業とは異なる操作が求められるため、特に注意深く操作し、誤操作を防ぐように努めなければいけません。
【クレーン機能付きバックホウを操作するときの安全事項】
・仕様で定められた荷重を超える荷物は、絶対に吊り上げないこと。
・油圧ショベルの旋回速度が速いため、エンジンの回転速度を低く設定し、作業切換装置が備わっている機械では低速に切り替えて作業を行う。
・合図者や玉掛作業者など関係する作業者との連携を密にし、指名された合図者が出す指示以外では運転しないように注意する。
・地盤の状況や周辺設備、関係作業者など周囲の安全確認を徹底する。
・取扱説明書を熟読し、正しい運転操作と日常点検を欠かさず実施すること。
このように、クレーン機能付きバックホウの使用では留意点が多くあるため、安全かつ効率的な作業を行うには、熟練のオペレーターによる操作が大切です。
また、オペレーター付きで重機をレンタルすると以下のようなメリットもあります。
プロの技術と経験を活用できる
バックホウやクレーンの操作は熟練を必要とする作業であり、特に複雑な地形や狭いスペースでの作業では、オペレーターのスキルが効率性と安全性に直結します。
時間とコストの削減
効率的な作業は、燃料費やその他の運用コストの削減にもつながるほか、操作ミスによる機械の故障や現場での事故を防ぐことで、修理費用のコストも削減できます


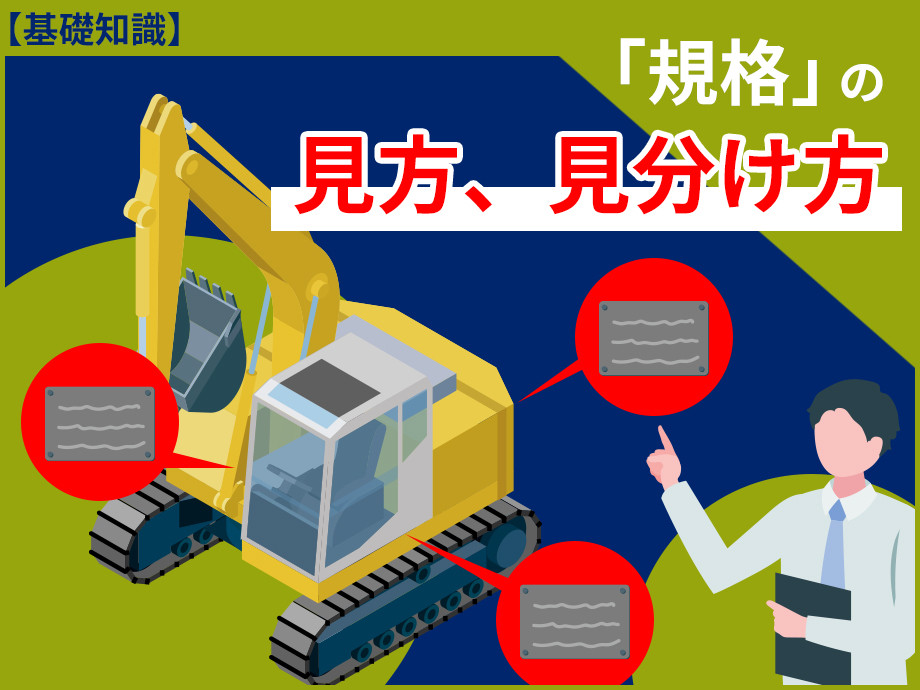
 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


