
ユンボ
2022/06/09
32,091
ユンボの整地作業のコツがわかる!操作に必要な資格も詳しく紹介!
ユンボの整地作業のコツがわかる!操作に必要な資格も詳しく紹介!

このように汎用性の高いユンボが得意とする作業の一つに整地作業があります。
整地とは、手を加えられていないでこぼこの土地を、不要物を撤去処分してフラットな土地に整備することです。
ユンボできれいに整地された土地は、見栄えが良く、価格を高く設定することができます。同時に、どんな土地活用をするにしても、すぐに工事に取りかかれる状態です。
この記事では、土地を活用するのに欠かせない整地作業と、作業に必要となるユンボの操作方法について詳しく紹介しています。
未使用の土地をどうしようか検討している方や、ユンボの現場での操作性を知りたい方はぜひ参考にしてください。
整地とは

不要な樹木や埋設物、廃材などがあれば撤去し、高低差や不陸(でこぼこ)は切土や盛土で平らにします。状況によっては、土を補充したり、逆に残土を搬出したりすることも必要です。
未使用の状態が長期間続くと、雨水で土砂が流出したり、草木が伸び放題になったりします。それらを防ぐため、排水のための勾配や排水設備を設置したり、表面に砕石を敷き詰め軽転圧したりすることもあります。
整地する区画の範囲が大規模になる場合は、計画する地盤の高さが分かるように丁張を出します。その丁張を目視で確認しながら、ユンボを稼働させなければなりません。
整地された土地は見栄えが良く、特に売り地にする場合は、購入予定者の印象を格段にアップさせます。
整地作業の手順

整地作業は、建物の解体工事の最終工程で行われることの多い作業です。逆に、住宅や施設の庭や外構のリフォーム工事では、最初に施工されます。
ここでは、一般的な整地作業の手順を紹介します。
解体や更地にしてから長期間放置された土地には、近隣の空き地の雑草が侵入してきたり、不法投棄物が堆積したりすることがあります。これらもきれいに撤去しなければなりません。
ユンボで支障物や不要物を集積し、種類ごとに分別しながらダンプに積込みます。ダンプ車は、それらのゴミを産廃(産業廃棄物)として、各処分場へ運搬し処分します。
産廃は、処分するのはもちろん、運搬するにも許可が必要です。廃棄の搬出業者と処分場は、工事ごとに契約が必要ですし、マニフェスト伝票による管理も求められます。
基本となるGL(計画地盤)を設定したら、土や砂利からなる原地盤を前向きに押しながら進み、クローラー(キャタピラ)の跡を消す場合は後ろ向きで引きます。低いところは盛土して平らにし、高い部分は掘削して切土します。
規模が大きな現場では、丁張を設置して地盤の高さを確認しながら作業しましょう。
整地作業面積が大規模になれば、ブルドーザーやトラクターショベルの使用も検討します。ただ、これらの重機はユンボと違って、敷均し以外の作業には使いづらいケースが多いです。
粗仕上げとは、不要物を撤去処分した後、ユンボで表土を均して完了とする仕上のことです。水勾配などの排水処理もしていないので、手間がかからない分、費用は安く済みます。
ただ、土地の活用方法が決まっていなくて、長期にわたって放置する可能性がある場合は、砕石舗装で仕上げることも多いです。
砕石舗装とは、表土上に10~15cm程度砕石を敷均し、ランマやプレートで締め固める舗装のことです。砕石は、角張っているので締まりやすく、軽微な舗装材としてよく使われます。
砕石舗装で仕上げることで、水が溜まりにくく、雑草も生えづらくなります。
ユンボの基本の操作方法


ユンボの基本構造
エンジンをかけて、油圧ポンプをまわし、圧油をモーターやシリンダーに送り出して動かします。モーターは走行部・旋回部、シリンダーは作業機部を動かします。
この力をバルブで制御するのが、コントロールレバーです。モーターやシリンダーは、圧油の流れる方向で回転や運動の方向が決まります。
つまり、ユンボの操作とは、圧油の流れる方向をコントロールすることなのです。
実は、ユンボというのは通称で、元々は、あるメーカーが製造した油圧ショベルの商品名でした。それが人気商品となり、商品名が油圧ショベルの代名詞のように一般に定着したのです。
ユンボの基本の操作

①前後操作でアームの押しと引き、左右操作で左旋回と右旋回
②前後操作で左クローラーの前進・後退
③前後操作で右クローラーの前進・後退
④前後操作でブームの下げと上げ、左右操作でバケットの閉めと開け
⑤安全用ロック
⑥各社の操作パターン一覧(詳しくは後述します)
⑦ブレードの上げと下げ
レバーの操作自体は簡単ですが、現場の状況に合わせて体感的に操作する必要があります。とにかく触って、慣れることが大切です。
ユンボのパターン別操作
操作パターンは、一度覚えてしまうと無意識に体が動いてしまうので、それを変えるというのは難しいことです。
そのため、操作方法を切り替えるマルチレバー装着車が増えています。操作方法を切り替えることによって、使い慣れた方法でユンボを操作することができます。
ユンボの運転席付近に、下記の画像のようなステッカーが貼ってあれば、そこの切り替え装置がついています。
ユンボの操作方法のコツ

これを覚えておくと、ユンボの操作性が上がってきます。
ここでは、ユンボの機体を、大まかに2つに分けて操作のコツを紹介します。
アームとブームを操作するコツ
アームだけを使う作業と、アームとブームの両方を使う作業がありますが、ポイントはいかに左右のレバーをバランスよく動かすかです。
左手でアームを引きながら、右手でバケットを開いたり閉じたり、ブームを上げたり下げたりします。慣れないうちは、ブームを高めに上げて、アームを引くようにします。
アームは、シリンダーとアームが直角のときに、押し出し力が最大になります。これも覚えておくと便利です。
掘削箇所に向かって機体を縦向き・横向きどちらに置くか、ブレードの位置をどうするかで、アームやブームの作業効率は変わります。スピードを優先するのか、力を必要とするのかを考えながら位置を選びましょう。
ブレードとクローラーを操作するコツ
上手くやるためのコツは、常に、ブレード(排土板)の水平を心がけることです。次に、自分の視点のポイントをブレードのどこか一点に決めて、機体と整地高さの位置関係を覚えておくことも大切です。
操作レバーは、細かいタッチで、微妙な動作を与え続けます。
ユンボの機体の大きさを体感的に把握することは、操作性を上げるための基本です。特に、ブレードやクローラー(履帯・キャタピラ)は、視界に入りづらいので操作に難しさを感じやすい部分です。
クローラーの操作でポイントの一つになるのが、ターンです。ターンには、スピンターンとピポットターンの2種類あります。
スピンターンは、左右のクローラーに取付けられたモーターをそれぞれ逆回転させて、その場でターンします。ピポットターンは、左右どちらかのクローラーだけを動かしてのターンです。
ユンボの操作・運転に必要な資格・免許

ホイール式の場合、ユンボに乗って公道を走る場合は、自動車免許が必要になります。必要な自動車免許は、車両総重量で変わります。
・車両総重量3.5t未満|普通自動車免許
・車両総重量3.5t以上7.5t未満|准中型自動車免許
・車両総重量7.5t以上11.0t未満|中型自動車免許
・車両総重量11.0t以上|大型自動車免許
また、鉄キャタのユンボは公道を走れません。ゴム(ホイール式)キャタでないと公道は走れないのです。
運転技能講習は、全国の登録教習機関で受講できます。
コースや受講用件は、保有している資格や業務経験で変わります。
| コース区分例 | 現在保有している資格や業務経験 |
| 6時間 | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者 |
| 18時間 | 小型車両系建設機械(整地など)特別教育終了後、機体総重量3t未満の車両系建設機械の業務経験が6ヶ月以上ある (特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付) |
| 38時間 | 未経験 |
特別教育というのは、事業者が作業者に対して行うことができるものです。しかし、実態としては各教習機関で受けることがほとんどです。
受講要件は特に無く、通常、学科(7時間)・実技(6時間)となっています。
学科のみを受講し、実技は各事業所で行う場合の費用は、概ね15,000円(税込)となっています。詳細は、地域の登録教習機関に事前に確認することをおすすめします。
まとめ



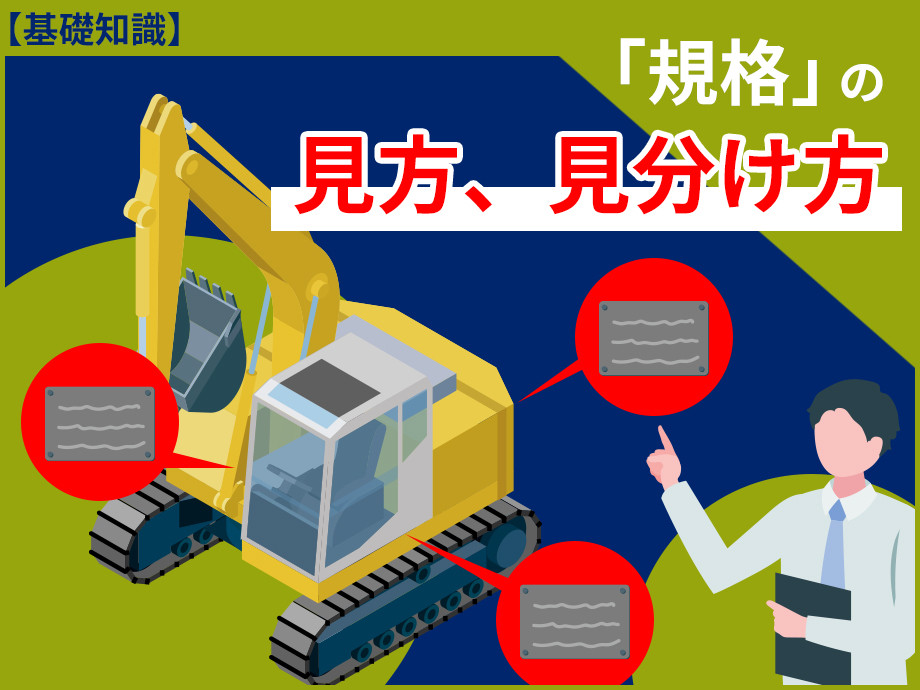
 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


