コスト削減のカギ!重機レンタル vs 購入の判断基準
建設現場で使用する重機は高額なため、なるべくコストを抑えながら導入したいという方も多いことかと思います。コスト削減のポイントは導入方法を慎重に選ぶことが大切です。
特に、「レンタル」と「購入」のどちらが適しているのかを見極めることが重要と言えます。本記事では、長期工事と短期工事におけるそれぞれのコスト比較や、適切な重機の導入方法について詳しく解説していきます。
この記事でわかること
重機の購入、レンタルのメリット、デメリット
リースのメリットと購入の比較
長期、短期レンタルの比較
重機の中古購入がおすすめのケース
重機の導入コスト削減!レンタルと購入の基本知識を解説
建設現場や土木工事、もしくは農業や林業などあらゆるシーンで不可欠な建設重機。導入には大きく分けて「購入」と「レンタル」という2つの方法があります。
近年、重機を新車で購入するというケースは少なくなっていますが、レンタルのデメリットを理解していないとコスト面でかえって損してしまう可能性もあります。
また、どちらを選ぶかによって、初期費用や維持管理費、運用の柔軟性が大きく変わってきます。それぞれの特徴を理解し、工事の規模や期間に応じて最適な方法を選択することで、コスト削減に繋がります。
重機の新車購入|2つの大きなデメリット
重機を新車で購入することは、機能性や信頼性などにおいて一見多くのメリットがあるように思えますが、一方で大きなデメリットも存在します。特にコスト面や運用面での負担が重く、新車購入には慎重な判断が必要です。
重機の新車購入における2つの主要なデメリットについて解説します。
デメリット1. 費用負担が大きい
建設機械などの重機は、大変高価なので新車購入には高額なランニングコストがかかります。
特に、昨今の原材料価格の高騰、物流費の上昇などの影響で建設機械やそれに使用される部品も軒並み価格改定が実施されています。中型バックホウの場合、機種にもよりますが新車は¥10,000,000前後の値段になるため、決して安い買い物とは言えないでしょう。
このように、建設機械を新車で導入するには、高額な初期投資を覚悟しなければなりません。計画性を持って購入しないと自社の資金繰りに影響を与えることにもなるほか、資金不足の場合は、新車購入のための予算調達が必要になり、結果によっては自社の財務体質を悪化させてしまう可能性もあります。
デメリット2. 納品まで時間がかる
重機の新車購入は、買ったからといって製品がすぐ手に入るわけではなく、納車期間があるため納品までに長い時間がかかります。
新車の建設機械の場合、メーカーが月に生産する台数が少なく、機種によっては発注を受けてから製造を開始する受注生産になります。また、一般的な納車期間は、1〜2年、大型機械になるとさらに製造期間が長期化する場合もあります。
そのため、すぐに業務で使用したい場合は、新車購入ではなく別の導入方法を検討するのが賢明でしょう。今後、その機種を使用する予定がある際も、納車期間を考慮して購入することが大切です。
重機レンタルのメリット・デメリット
昨今の建設現場や土木現場では、重機を1台ずつ購入して揃えるよりも、重機をレンタルで賄う企業が一般的となっています。
建設機械の価格は高額であるほか、維持管理、修繕、保管、保険料などのコストに加えて、資産保有に伴う固定費負担が所有のネックです。そのため、企業、個人問わず、利用者は重機を保有するのではなく、作業内容などに合わせレンタルを活用することで固定費の変動費化を図ることができます。
重機レンタルには初期費用や維持費の削減やメンテナンスの手間を省くなどのメリットがありますが、一方で無視できないデメリットも存在します。
重機レンタルのメリットとデメリットを詳しく解説していきます。
重機レンタルのメリット3つ
重機レンタルのメリットは、導入費や維持にかかる費用負担の軽減、高機能な機種を使用できるという面にあります。以下では、重機レンタルのメリットを3つに分けて解説していきます。
導入コストがもっとも安い|必要時に必要数レンタルできる
建設機械を新車で購入する場合、数百万〜数千万の初期投資が必要になります。大企業ならまだしも、中小企業が、重機を必要数新車で揃えることは難しいです。
しかし、レンタルであれば、レンタル費用を払うだけで必要なときに必要な台数だけ重機を借りることができるため、導入にかかるコストを大幅に抑えられます。
特に、1日だけ借りたいという場合や短期間の工事など、一時的に特定の機械が必要な際は重機レンタルを利用するのがもっとも最適でしょう。
維持コストが不用|メンテナンスや車検・検査などの費用負担がない
重機所有には、維持するための定期的な点検・整備やそれに伴う費用、そして車検や保険料などの維持費も追加でかかります。しかし、レンタルならばメンテナンスやそれらの維持費用はレンタル会社が負担するため、管理の手間やコストを削減を削減できます。
人材不足が深刻化する建設業界ですが、特に、小規模な事業者にとっては大きなメリットです。
状態の良い重機がいつでも使用可能|最新の機種を気軽にレンタルできる
レンタル会社では、メンテナンス済みの重機を貸し出しているため、常に良好な状態の重機を使用できます。また、レンタル会社の在庫状況にもよりますが、最新モデルの機種もレンタルできるため、GPS搭載やICT施工などに対応したモデルであれば、最新技術を活用した作業も可能になります。
一度重機を購入すると、長期間同じ機種を使い続ける必要がありますが、レンタルならば必要に応じて最新の機種を利用できます。自分で購入する前に最新機種を試したい、という場合でもレンタルを活用することもできます。
重機レンタルのデメリット3つ
重機レンタルのデメリットは、レンタル期間、機種の選択肢、在庫の問題などが挙げられます。
長期的なレンタルは費用負担が大きい
重機レンタルは短期間の利用に適していますが、長期的にレンタルを続けると費用が高額になってしまうというデメリットがあります。
そのため、レンタルを利用する際には、工期や作業計画と照らし合わせた上で、レンタルを検討することが重要です。
年単位で継続的に機械を使用したい場合は、リースや購入を検討した方が経済的な場合もあります。
機種の幅(選択肢)が少ない
各レンタル会社が取り扱う重機の種類、保有数には限りがあり、必ずしも希望する機種がレンタルできるとは限りません。
水中工事や林業用など特殊な作業に必要な機種や、特定のメーカー機種が使用したい場合は、選択肢が広いリースもしくは購入も視野に入れて検討してみてください。
繁忙期は希望機種がレンタルできないこともある
レンタル会社が保有する重機の在庫には限りがあるため、時期やタイミングによっては、希望する機種が在庫切れでレンタルできないこともあります。
建設業界の繁忙期は、一般的に9月末と12月〜3月末頃と言われ、決算期や新年度の工事が集中する時期に業務量が大幅に増加します。そのため、繁忙期は需要が集中し、重機が予約で埋まることも珍しくはありません。特に、大型の工事が多い時期には、希望の機種が確保しづらくなることが予想されるため、早めにレンタルの予約をすることをおすすめします。
重機リースとは?|重機をリースするメリット、購入との比較
重機の調達方法として「レンタル」以外に、「リース」という選択肢もあります。リースは、会社が重機を購入しない代わりに一定期間の契約を結び、使用料(リース代)を払い続けることで長期間に渡り重機を使用する方法です。
リースはレンタルや購入とは異なるメリット・デメリットが存在します。レンタルとリースの違いや、リースの活用方法について詳しく解説します。
レンタルとリースの違い
レンタルは、短期間の使用を目的とし、数日〜数か月単位で重機を借りる方式です。それに対しリースは、数年単位の長期契約となり、契約期間中は継続的に同じ重機を使用できます。リース期間は法律で定められており、大抵は3〜5年という長期間になるでしょう。
リース契約は長い間安定して使用する場合に適していますが、基本的に途中解約が難しいため、注意が必要です。
長期使用する場合は重機リースがおすすめ
長期的に重機を使用する場合、レンタルよりもリースの方がコストを抑えられる可能性があります。リースでは、毎月一定額の支払いで済むため、資金計画が立てやすいのもメリットです。また、リース契約にはメンテナンスや保険が含まれる場合もあり、管理の手間を減らすことができます。
リース契約の注意
リース契約にはいくつかの注意点があります。
重機の調達方法として「レンタル」以外に、「リース」という選択肢もあります。リースは、会社が重機を購入しない代わりに一定期間の契約を結び、使用料(リース代)を払い続けることで長期間に渡り重機を使用する方法です。
リースはレンタルや購入とは異なるメリット・デメリットが存在します。レンタルとリースの違いや、リースの活用方法について詳しく解説します。
レンタルとリースの違い
レンタルは、短期間の使用を目的とし、数日〜数か月単位で重機を借りる方式です。それに対しリースは、数年単位の長期契約となり、契約期間中は継続的に同じ重機を使用できます。リース期間は法律で定められており、大抵は3〜5年という長期間になるでしょう。
リース契約は長い間安定して使用する場合に適していますが、基本的に途中解約が難しいため、注意が必要です。
長期使用する場合は重機リースがおすすめ
長期的に重機を使用する場合、レンタルよりもリースの方がコストを抑えられる可能性があります。リースでは、毎月一定額の支払いで済むため、資金計画が立てやすいのもメリットです。また、リース契約にはメンテナンスや保険が含まれる場合もあり、管理の手間を減らすことができます。
リース契約の注意
リース契約にはいくつかの注意点があります。
途中解約ができない
契約期間内にリースを解約すると違約金が発生してしまうため、契約と契約内容の確認は慎重に行う必要があります。
所有権がない
リースの場合、契約満了後も重機は自社の資産にはならず、再契約または返却が必要です。
メンテナンス条件を確認
契約内容によっては、定期メンテナンス費用が別途発生する場合があります。
リース契約の費用はどのくらい?
リース契約の費用は、重機の種類や契約期間によって異なります。
一般的に、リースにかかる費用は”月額数万円〜数十万円”の範囲で設定されており、契約内容によってはメンテナンスや保険料が含まれることもあります。使用期間などによってはレンタルよりも割安になるケースもあるため、長期間使用する場合はリースの方が経済的です。
重機の中古購入するメリットとは|どんな人が向いてる?
重機の導入方法として、「新車購入」「レンタル」「リース」を紹介しましたが、コストを抑えつつ設備投資をしたい事業者は重機の「中古購入」がおすすめです。
重機の中古購入が向いているケースや中古購入のメリットについて詳しくご紹介します。
新車購入より導入コストを抑えたい
新車の重機は、種類によっては数千万円以上の高額な投資が必要です。一方、中古重機であれば、新車の「50〜70%程度」の価格で購入できることもあります。
予算を抑えながら必要な重機を導入したい場合に、中古購入は有効な手段です。
主力機種を複数台揃えたい
作業内容や現場、事業者によっては、同種類の機種を複数台必要とすることがあります。しかし、新車を何台も購入するのはコスト面での負担が大変重くなります。
中古ならば重機を比較的安価に複数台を揃えることが可能で、業務の効率化につながります。
すぐにその機械を使いたい
新車の重機は、注文から納品まで数ヶ月〜1年以上かかることがあります。中古重機であれば、在庫があれば即納品が可能なため、急ぎで導入したい場合に適しています。
特に、突発的な工事や機械の故障、急な業務拡大に対応するには、中古購入が有利です。
市場にあまり出回っていない機種で欲しい重機がある
今は生産が終了している、あまり出回っていないなど、特定のメーカーや旧型機など、手に入りにくい重機が必要な場合も、ネットオークションなどの中古市場で探すのがおすすめです。
特に、特殊な用途で使用する重機や廃盤になったモデルは、中古市場だけで入手できることが多いので、もしかしたら探していた希望機種が見つかるかもしれません。
重機購入の判断|長期工事・短期工事のコスト比較
重機を導入する際は、どの導入方法がコスト的に有利かを考えて判断することが大切です。
長期工事と短期工事のコストを比較し、ケースごとに有利な導入方法を解説していきます。
短期・長期の重機レンタル料金を比較
重機のレンタル料金は、一般的に日割りか月極(月割り)料金で設定されています。短期間の利用にはレンタルが適していますが、長い間レンタルを利用しようとすると費用が高額になり、結果として中古機械を購入した方が安かったということもあります。
そのため、レンタルか購入を検討する際は、工事の期間に応じて適切な導入方法を選ぶことが大切です。
以下で、一般的な建設機械のレンタル費用目安を一覧表にまとめましたので参考にしてみてください。
レンタル料金は、機種・地域・レンタル会社・レンタル期間によって異なるため、具体的な価格は各レンタル会社のホームページで確認するか、直接問い合わせて見積もりを確認してください。
機種名
日額料金(円)
月額料金(円)
ミニショベル(0.1㎥)
8,000~15,000
150,000~250,000
バックホー(0.25㎥)
15,000~25,000
300,000~500,000
バックホー(0.45㎥)
25,000~40,000
500,000~800,000
ホイールローダー(小型)
10,000~20,000
200,000~400,000
ホイールローダー(大型)
25,000~50,000
500,000~1,000,000
ブルドーザー(小型)
40,000~80,000
800,000~1,500,000
ブルドーザー(大型)
40,000~80,000
800,000~1,500,000
クレーン(25t)
30,000~50,000
600,000~1,000,000
クレーン(50t)
50,000~80,000
,000,000~1,600,000
高所作業車(10m)
8,000~15,000
150,000~250,000
高所作業車(20m)
15,000~25,000
300,000~500,000
ダンプトラック(4t)
10,000~18,000
200,000~350,000
ダンプトラック(10t)
20,000~30,000
400,000~600,000
保険・メンテナンス費用が別途必要な場合もあり、故障時の修理費用や損害補償が含まれるかは契約内容によります。詳細な料金を知りたい場合は、建設機械レンタル会社へ直接見積もりを依頼しましょう
※価格はあくまで目安としてお考え下さい。2025年4月 トクワールド調べ
長期工事の場合は購入が有利
長期間にわたる工事では、重機レンタルを利用するよりも購入の方がコスト面や業務効率化で有利になります。
トータルコストが安い
レンタルは、日額料金よりも月極料金の方が割安になることが多いです。ただし、年単位の長期レンタルで利用する場合、月額料金が積み重なり多額な費用になることもあります。
特に、数年単位で使用したい場合は、中古購入した方がコストを抑えられる可能性が高くなります。
維持管理の自由度が高い
レンタル重機は、定期メンテナンスのスケジュールが決まっていることもあります。そのため、重機の在庫保有数が少ないレンタル会社の場合、点検やメンテナンスのために現場から重機を一度返納したり、それが完了するまでレンタルできないということもあります。
自分で購入した重機であれば、工期や使用時期を考慮して任意のタイミングでメンテナンスができるため、より柔軟な運用が可能になります。
資産として計上できる
購入した重機は、会社の資産として計上でき、減価償却(購入費用を使用期間中に分割して経費計上する会計処理のこと)による節税もできるメリットがあります。
一方、レンタル費用は損金として経費にできますが、資産にはならないため、長期的な視点で考えると購入の方が財務的に有利な場合があります。
短期工事の場合はレンタルが適切
短期間の工事では、重機を購入するよりもやはりレンタルの方が適しています。
ランニングコストが不要
重機の購入後は、維持管理費、税金、保険などのさまざまなランニングコストが発生します。しかし、重機レンタルであれば、利用した期間分の費用だけを支払えば良いので、コスト管理がしやすいです。
重機の維持・管理が不要
機を自分で管理しなくて良いという面も重機をレンタルする大きな利点です。
レンタルであれば、車検、定期点検、修理などの管理業務はレンタル会社が行うので、企業側での維持負担は発生しません。そのため、メンテナンスの手間やコストを削減できます。
必要な機種を必要時だけレンタルできる
工事の内容によって必要な重機が変わりますが、レンタルを利用すれば、工事内容に応じて最適な機種を必要数選べます。また、作業で使用するアタッチメントもレンタルできるため、重機やアタッチメントをその都度飼いそろえるよりも遥かにコストパフォーマンス性に優れています。
まとめ
重機の導入には「新車購入」や「中古購入」、「レンタル」、「リース」などの方法があります。新車購入は、やはり価格が大きなネックとなるので、自分の機械が欲しいという場合は中古車購入が現実的かもしれません。
導入コストを削減するには、それぞれの工事規模や工期、経営戦略などを考慮して、それぞれの事情に適したもっともベストな導入方法を選ぶことが大切です。
#レンタル#ユンボ#バックホー#油圧ショベル

2,032
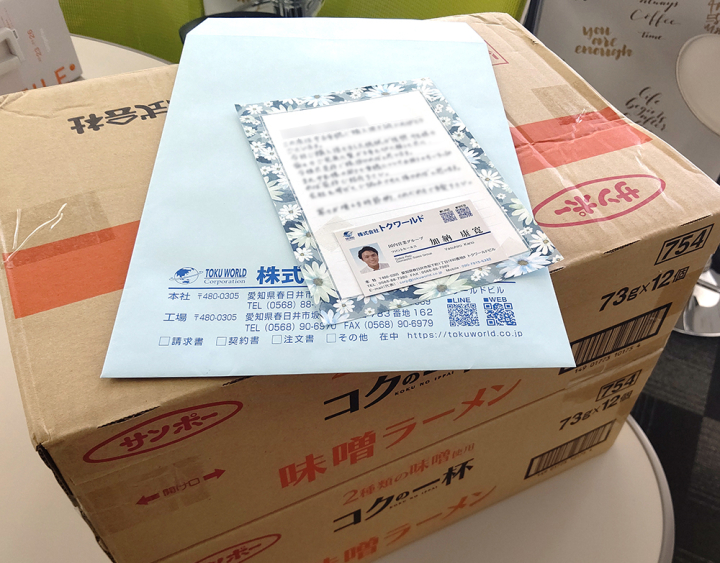




 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


