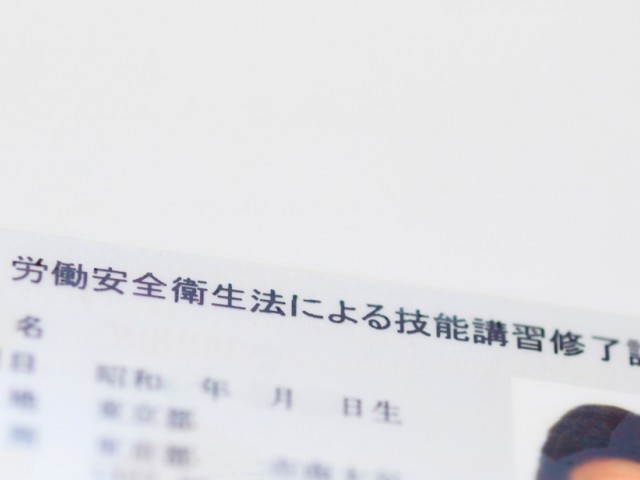
フォークリフト
2023/03/01
15,856
フォークリフト免許が丸わかり!資格取得の方法から費用まで全解説!
「フォークリフトの免許があれば就職に有利ってホント?」
「フォークリフトの免許を取るのに必要な費用や日数を知りたい」
フォークリフトは物の運搬を必要とするあらゆる場所で活躍しています。
代表的なのは倉庫や工場、建設現場などですが、物を「積む・降ろす・運ぶ」という仕事を必要とする業種は数多くあり、フォークリフト運転手の需要は高いです。
ただ、公道を走る一般的な自動車とは扱いが違うため、免許を取る方法については意外と知られていません。
公道を走る自動車の運転免許は、国土交通省の管轄で道路交通法に基づいています。これに対して事業場内で働くフォークリフトの運転に関する資格は、厚生労働省の管轄で基づくのは労働安全衛生法です。
この記事では、フォークリフトの免許を取る方法と必要な費用や日数について詳しく解説しています。最後まで読んでいただければ、フォークリフトの免許を取るための行動をすぐにでも起こせるはずですからぜひ参考にしてください。

フォークリフトを運転するには資格が必要
その点、フォークリフトを運転する資格取得のメリットは大きいです。
現在、物流ニーズが高まっていて、倉庫での各種作業に欠かせないフォークリフト運転手のニーズも右肩上がりです。その他、製造工場や部品メーカー、大型ショッピングセンターやスーパーなどの倉庫内業務でもフォークリフト運転手は活躍しています。
フォークリフトを使っての作業は、特別な体力や腕力を必要としないので女性にもこなすことができます。
フォークリフトを運転する資格は、一度取得すれば更新の必要はなく年齢制限もないため、一定の能力さえあれば高齢になっても仕事をすることが可能です。
以上のことから、フォークリフトを運転する資格の取得はメリットが大きいといえるのです。

フォークリフトを運転する資格には2種類ある
1t以上のフォークリフトを運転する資格
「フォークリフト運転技能講習修了証」は、厚生労働省管轄の労働安全衛生法に基づく国家資格です。
運転技能講習には学科と実技があって、両方の修了試験に合格しなければなりません。
学科教育では、フォークリフトの走行に関する装置の構造や取り扱い方法と、フォークリフトの荷役に関する装置の構造や取り扱い方法について学習します。その他、フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識と関係法令についても学びます。
実技教育は、フォークリフトの走行や荷役の操作の実践を交えながらの学習です。
受講科目は、保有する資格によって免除されるので事前に確認しておきましょう。
フォークリフト運転技能講習は、都道府県労働局長の登録認可を受けた教習機関で行われます。
1t未満のフォークリフトを運転する資格
このフォークリフト運転特別教育は、基本的に事業者が主体となって行うものです。ただ学科教育に関しては、ほとんどの場合、教習機関によって行われているのが現状です。
学科教育の講習内容は、フォークリフトの走行や荷役に関する装置の構造及び取り扱い方法、運転に必要な力学の知識と関係法令になります。概要は運転技能講習と同様ですが、学習時間は大幅に短縮されます。
実技教育を行うのは、通常では所属する各事業所ですが各教習所でも可能となっています。
教育時間としては、フォークリフトの走行の操作は4時間以上、荷役の操作に関しては2時間以上というのが目安として設定されています。

フォークリフト運転技能講習について徹底解説
合格率は非公開となっているのですが、Web上で調査すると、「96%」「90%~98%」「99%」などの記述が多く非常に高いものとなっています。
学科教育では試験に出題される内容を教えてくれるとか、実技試験に合格できるレベルまで練習できるとか、試験当日に再試験が受けられるというような情報も見受けられました。ただ、現在も行われているのか、どの試験会場でも行われているのかまでは把握できていません。
興味や関心がある方は、国家資格ということに臆することなく挑戦してみる価値はあるでしょう。
フォークリフト運転技能講習修了証について詳しく紹介します。
フォークリフト運転技能講習修了証の受講資格
年齢制限もないのですが、18歳以上でなければ年少者の就業制限(年少則第8条第7号)があるため資格があっても就業することはできません。
受講の際、保有している免許や資格によって免除される科目などがあります。以下にその概要をまとめました。
| 保有する資格 | 免除される科目など |
| ・大型特殊自動車免許(カタピラ限定なし)を有する者 ・大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許(カタピラ限定有)を有し、3ヶ月以上最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務に従事した者 |
・走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ・走行の操作 |
| 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許(カタピラ限定有)を有する者 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
| 6ヶ月以上最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務に従事した者 | 走行の操作 |
| その他の者 | 免除なし |
フォークリフト運転技能講習の受講方法
以下は、講習予約から資格取得までの流れです。
1.受講コースと日程を選ぶ
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/tokyo/application_info.html
上記URLにアクセスして、「講習日程を見る」をクリックし、フォークリフト運転技能講習を選択し講習の空き状況を確認しましょう。
2.予約する
空き状況の確認ができたら、必ずWeb又は電話(042-632-0635)で予約します。
3.申込み
予約受付日を含め10日以内に、受講申込書に必要書類を添付して申込みします。FAX又は郵送で申込み可能です。
4.受講票の確認
申込みが完了すると、受講票と振込確認書がFAX又は郵送で送られてきます。書類提出後、2~3日経っても送られてこないときは事務局に連絡して確認してください。
5.受講費用の支払い
受講日の3日前(土日祝含まず)までに振込します。振込手数料は当方負担ですから注意しましょう。
6.受講当日
受講当日は朝8時までに来所してください。写真撮影後、各教室で受付があります。詳しい注意事項はWebで確認してください。
7.修了・修了証交付
規定の講習時間を受講し、試験に合格すると修了証が即日交付されます。
詳細については、自分の地域の登録教習機関に問い合わせましょう。全国の登録教習機関は、以下のサイトで検索できます。
厚生労働省|登録教習機関一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei05.html
フォークリフト運転技能講習の受講時間
| コース区分 | 現在保有している資格及び業務経験 |
| 11時間 | ・大型特殊免許(カタピラ限定を除く)所有者 ・普通、準中型、中型、大型、大型特殊(限定あり)免許を有し、小型フォークリフト特別教育修了後、最大荷重が1t未満のフォークリフトの業務経験が3ヶ月以上ある方 (特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付) |
| 15時間 | 小型フォークリフト特別教育修了後、最大荷重が1t未満のフォークリフトの業務経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付) |
| 31時間 | 普通、準中型、中型、大型、大型特殊(限定あり)免許所有者 |
| 35時間 | 上記のいずれにも該当しない方 |
各登録教習機関によって実施していないコースもありますから事前に確認しておきましょう。
フォークリフト運転技能講習の受講費用
| コース | 日数 | 受講料(税込)テキスト代含む |
| 11時間 | 2日 | 23,000円 |
| 31時間 | 4日 | 51,000円 |
| 35時間 | 5日 | 51,000円 |

フォークリフト運転特別教育について徹底解説
労働安全衛生法では、特別教育は事業者(事業を行う個人・法人・団体)が行わなければならないと規定しています。しかし実際には、ほとんどのケースで登録教習機関が代行しているのが現状です。
フォークリフト運転特別教育について紹介します。
フォークリフト運転特別教育の受講資格
ただ、フォークリフトの運転で就業するには18歳以上でなければなりません。ですから、18歳以上というのが実質的な受講資格ということになるでしょう。
フォークリフト運転特別教育の受講方法
1.受講コースと日程を選び予約・申込み
2.受講票の確認・受講費用の支払い
3.受講・修了・修了証交付
まず自分が住む地域に近い登録教習機関を調べて、Webを確認するか、電話で問い合わせてみましょう。
厚生労働省|登録教習機関一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei05.html
講習日程を予約する際は、講習名を間違わないようにしてください。特別教育と安全衛生教育との間違いが多いようです。
フォークリフト運転特別教育の受講時間
学科は、まず走行と荷役に関して2時間ずつ、装置の構造や取り扱い方法の知識についての学習です。その後、運転に必要な力学の知識と関係法令について1時間ずつ学びます。
実技は、走行の操作に4時間と荷役の操作について2時間、実践を中心に受講します。
フォークリフト運転特別教育の受講費用
受講費用は、各地域、各登録教習機関で違いがありますので直接確認するようにしましょう。

フォークリフトの運転資格で助成金を申請する方法
雇用保険給付制度の「教育訓練給付制度」を利用すると、フォークリフト運転技能講習にかかる費用を最大20%返金してもらえます。
この教育訓練給付金制度について紹介します。
教育訓練給付金制度とは
この制度の教育訓練の種類は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3つです。
フォークリフト運転技能講習は、一般教育訓練に該当します。一般教育訓練では、受給要件を満たす対象者が受講・修了した後、ハローワークを通じて申請すると最大20%(上限10万円)が返金されることになっています。
教育訓練給付金の支給対象
納付期間は、教育訓練の種類によって違うため、ここではフォークリフト運転技能講習が含まれる一般教育訓練についてのみ説明します。
一般教育訓練では、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上必要です。初めて支給を受けようとする場合のみ、1年以上でOKとなります。
また退職者は退職の翌日から起算して1年以内に受講を開始しなければならないので注意が必要です。ただし、妊娠や出産などの事情がある場合は4年以内となっています。
同じ人が短期間に何度も申請することはできません。前回の訓練給付金の受給から3年以上経過していることが必要です。
教育訓練給付金の手続きについて
一般教育訓練給付金の支給申請期限は教育訓練の受講終了日(修了証受領日)の翌日から起算して1ヶ月以内です。
1ヶ月は短期間です。支給対象となる方は受講前から事前準備して、修了証を手にしたらすぐに申請するくらいの心構えで臨むことをおすすめします。

フォークリフト運転資格を活かして働ける業種
大量の荷物を効率よく荷捌きする物流業、資材や機材の搬入搬出が必要な建築業、商品や材料の在庫管理が欠かせない製造業などが代表的な業種です。
その他、人と荷物の移動に欠かせない港湾や空港などのターミナル、処分や再利用に分別が必要になる産廃処理場やリサイクルセンターでもフォークリフトは活躍しています。
業種によって、フォークリフトの機種や荷物の扱い方に差はあっても、基本となるフォークリフトの操作さえしっかり押さえておけば問題なく対応できるはずです。
フォークリフトの運転資格は比較的取りやすく、特に運転技能講習は国家資格です。資格取得に多少の時間と費用がかかったとしても、取得しておいて間違いのない資格といえるでしょう。
- フォークリフトを運転する資格は厚生労働省の管轄
- 最大荷重が1t以上は運転技能講習、1t未満は運転特別教育
- 運転技能講習の詳細(受講方法・受講時間・受講費用など)
- 運転特別教育の詳細(受講方法・受講時間・受講費用など)
- 最大20%が返金される教育訓練助成金を申請する方法
- 運転資格を活かして働ける業種
転職や再就職に有利な資格を探している方は、まずフォークリフトの運転技能講習を検討されてはいかがでしょうか。



 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


