
整備・修理
2023/01/26
21,836
ガソリン車・ガソリン発電機用燃料を備蓄したい|ガソリンを自社で備蓄・給油する方法
しかし、ガソリンの扱いについて知らない人が多すぎるというのも事実です。揮発性が高く引火点が低い特徴を持つガソリンは、扱いを間違えれば大きな事故に発展する可能性があります。
また、取り扱いに細かい規定は定められているため、いい加減な管理をしていると消防法違反となり、罰金もしくは逮捕されてしまうことも。
そこで今回は、ガソリンを私有地でも備蓄、セルフ給油する方法を紹介していきます。
災害時はガソリンが不足する
大規模災害といえば、今後30年以内で70〜80パーセントの発生確率があるとして政府や各市町村が備えを進める「南海トラフ地震」の話題も度々メディアで報道されています。
2023年1月には、「政府の地震調査委員会が、南海トラフで今後20年以内に巨大地震が発生する確率を「50〜60パーセント」から「60パーセント程度」に引き上げた」(2023年1月13日讀賣新聞より)という発表があり、年明け早々のトレンドとなりました。
また、いつ噴火してもおかしくないとされる富士山も、噴火時は首都圏でも降灰による交通網の麻痺、通信障害など甚大な被害が予測されています。
建設業はこのような未曾有の大災害に対し、直ちに業界をあげて対応し、被災地の復旧や復興にあたります。東日本大震災では「燃料不足」が深刻化し、復旧作業最大の課題になったことが調査報告(東日本大震災における建設業の災害対応実態調査報告書)で明らかになっています。
もはやいつ地震が起きても不思議ではない状況に、昨今では政府や各自治体だけではなく民間企業や会社でも災害への備えが進められ、「燃料の備蓄」が見直されています。
発電機や自動車の燃料として利用されるガソリンですが、ガソリンスタンドが遠い場所にあったり、大雪で道路が通行できなくなるような田舎では、会社や農家が私有地で備蓄していることも珍しくありません。

燃料不足・備蓄の見直しが課題
「東日本大震災における建設業の災害対応実態調査報告書」によると、発災直後から1週間以内の課題は通信ができないことと、燃料をどうやって入手するかということだったそうです。
特に燃料の確保は厳しく、資材や物資を運ぶ運送会社は燃料の手配がついてないと動いてくれなかったという状況も記載されています。
大規模な災害の直後は道路の寸断などにより、物流がストップするため燃料の輸送も困難な状況になります。被災地や周辺のガソリンスタンドにも燃料を求めて車が殺到するので、平素からの備蓄が重要です。
自然災害時には燃料が不足するという事象は、熊本地震、西日本豪雨、福井豪雨といった過去に発生した災害でも問題になっています。東日本大震災を教訓とした対策が施行されていますが、引き継ぎや連携不足などでその対策も未だ十分とはいえないようです。
東日本大震災時は3月でしたが、東北はまだまだ寒波と雪の降る季節だったため、ストーブに必要な灯油や、広範囲の地域が津波で被災したため瓦礫を撤去する重機の軽油も大量に必要でした。
ガソリンを大量保管することはできるのか?
そのため、安易にガソリンを大量備蓄することは勧められません。なぜなら、引火性や揮発性が高いガソリンを一箇所に長期間保管することは大変危険であり、法令違反になる場合もあるからです。
また、ガソリンは大量保管や長期間の備蓄に向かないというデメリットがあります。
以下で詳しく解説していきましょう。

個人で保管できる量は40Lまで
また、個人で保管できるガソリン40リットル未満とされており、それ以上のガソリンを保管するには設備の整備や届出が必要です。
ガソリンは劣化する
使う前提での保管が必要
しかし、ガソリンは半年以上の保管ができず、爆発する危険のある物質を長期間放置するのもおすすめはできません。そのため、日常的に使いながら保存する、非常食で言う「ローリングストック法」のような備蓄方法が望ましいでしょう。
しかし、それほど常にガソリンを使用しないという場合でしたら、近頃はカセットボンベを使用する発電機やガソリンの缶詰といった商品も出ているので、災害時用に備蓄しておくという手もあります。
ガソリンを自社で備蓄、給油する方法
消防法では、許可を受けた施設以外では、ガソリン200リットル以上を貯蔵又は取扱いすることを禁止しています。
しかし、ガソリンを自社で備蓄または給油する方法はいくつかあります。
①給油所等を設ける方法
200リットル以上を貯蔵、取り扱う場合は、自社車両への給油目的で「自家給油取扱所」、その他「簡易タンク貯蔵所」の設置を行う。
②震災時等の仮貯蔵・仮取扱いの申請する方法
事前に消防へ申請をしておき、震災時等に外部よりガソリン等を入手し、申請内容に基づいた貯蔵取扱を行う。
③少量危険物貯蔵取扱所を設ける
200リットル未満の保管とし、少量危険物貯蔵取扱書を設置する。
ガソリンは購入の規制も強化されている
2019年7月に発生した「京都アニメーション放火事件」では、容疑者がガソリンをまいて放火したことで多くの犠牲者が出たことから、ガソリン販売に関する規制も強化されました。

セルフスタンドでは購入できない。
セルフスタンドが許可されているのは、二輪車や四輪車への給油のみで、ナンバープレートが装着されていない車両への給油は禁止されています。それと同時に携行缶などのガソリン小分け販売も禁止されています。

専用携行缶を使う
5リットル、10リットル、20リットル(上限)の3つの容器があり、一般的に赤く塗装されています。そのほか、消防法に適合したジェリカンも使うことも可能です。
灯油用の赤いポリタンクにガソリンを入れようとする方は想像以上に多いようですが、消防法で禁止されているので注意してください。
身分証提示が義務化
・本人確認について
運転免許証、マイナンバーカード、公的機関が発行する写真付きの証明証の提示が必要。
・使用目的の確認について
「農業用機械器具の燃料」、「発電機用の燃料」、等の具体的な内容の確認が必要。

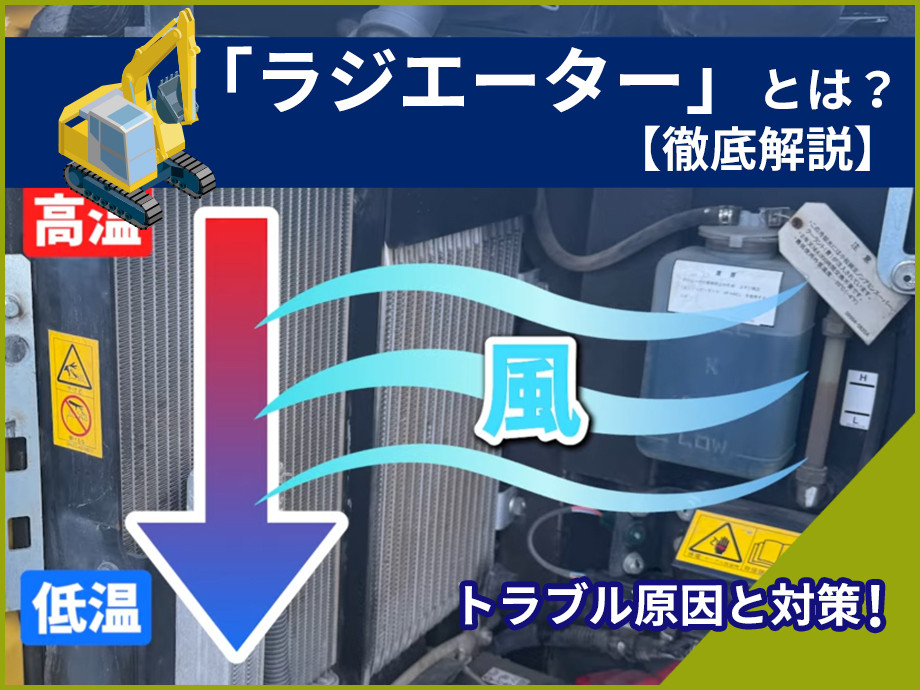

 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


