
建機
2021/10/07
2,355
重機の処分方法を解説!買取のメリットや流れは?
重機の処分方法を解説!買取のメリットや流れは?
重機を処分する場合の主な方法は、解体処分、買取、下取りです。
本記事では、重機の処分方法や買取の流れについて詳しく解説していきます。
重機の処分方法は3つ
重機の処分方法は主に解体処分、買取、下取りの3つです。それぞれ詳しく紹介します。

1. 解体業者に解体処分を依頼
まずは、解体業者に解体処分を依頼する方法です。いらなくなった重機を解体業者に依頼することで、引き取りから解体までの一連の作業をお願いすることができます。
また、故障している重機でも問題なく処分ができるので、処分に困ることもありません。
依頼するにはお金が掛かってしまいますが、確実に処分できるので、買取や下取りが難しい場合に利用しましょう。
2. 買取業者に買取を依頼
次は、買取業者に依頼して買い取ってもらう方法です。買取専門店に処分したい重機を査定してもらうことで、直接買い取ってもらうことができます。重機の状態やメーカーなどによって買取金額が決まるため、予想以上に高く買い取ってもらえる可能性もあります。
処分費用を掛けずに済むので、まずは買取から検討するのがおすすめです。
3. 販売業者に下取りを依頼
最後は、重機の買い替え時に下取りとして処分する方法です。新しい重機を購入する際に、販売業者に依頼することで下取りできます。しかし、販売業者は下取りに積極的ではないため、買取価格よりも安くなることがほとんどです。高値で売却したいのであれば買取を選びましょう。
重機の買取のメリット
処分する際にまずおすすめしたい方法が買取です。重機の処分に買取がおすすめな理由について詳しく解説しましょう。
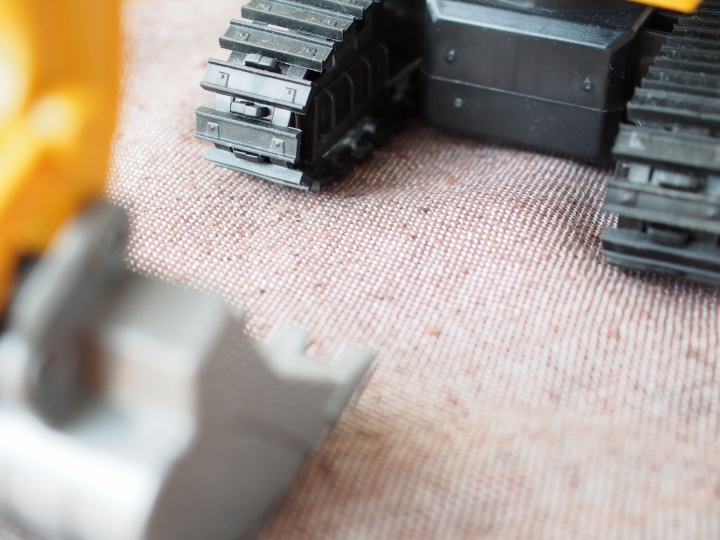
1. 故障していても売れる
買取は、重機が故障していても買い取ってくれるケースがあります。買取業者は重機本体だけでなく部品等も再販しています。
また、買取業者は修理技術も備わっているので、状態によっては修理も可能です。そのため、部品に価値があれば故障していても買い取ってくれるのです。
2. 買取価格が高額になることがある
買取業者によっては、重機の買取価格が相場より高額になることもあります。買取業者は多くの再販ルートを持っており、重機を高値で売る経験やノウハウがあります。
特に日本メーカーの重機は海外でとても人気なので、海外への再販ルートを持っている買取業者は日本で売るより高値で販売できるのです。
高値で買い取っても利益を出せるような業者であれば、高額売却が期待できるでしょう。
買取ってもらうまでの流れ
ここからは、実際に買い取ってもらうまでの流れや準備すべき書類まで紹介していきます。
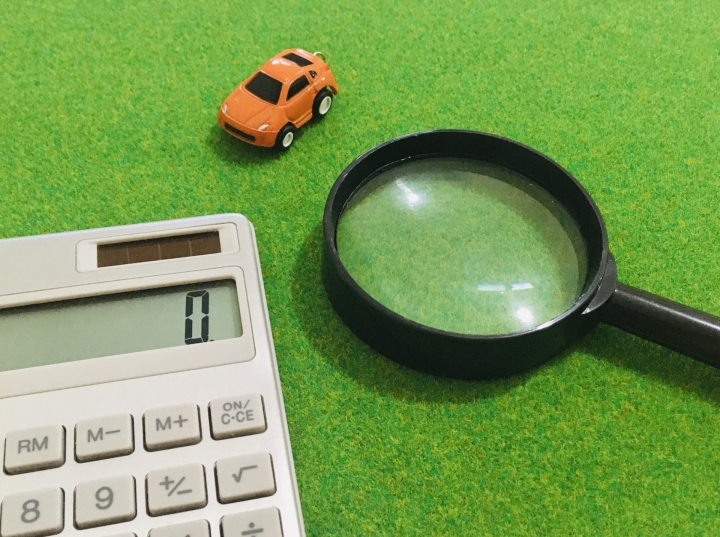
買取業者に無料査定を申し込み
まずは、買取業者に無料査定の申し込みをしましょう。申し込みは電話やインターネットから行えます。この時に重機のメーカー、機材の型式、能力表示などを伝える必要があるので、事前に調べておく必要があります。
申し込み後は、買取業者から概算による買取金額の連絡がくるので、金額に問題ないか確認しましょう。
重機の買取査定
概算による買取金額に問題がなければ最終査定に進みます。最終査定では、買取業者が実際に現物確認を行い、車の状態や書類などを確認して正式な買取金額を提示します。
買取金額に問題がなければ、このまま買い取ってもらいましょう。
契約に必要な書類を準備
売却が決まれば契約に必要な書類を準備しましょう。重機の大きさによって必要な書類が異なるので、下記に詳しくまとめておきます。・大型特殊自動車の場合
車検証、自賠責保険証明書、納税証明書、譲渡証明書
委任状、印鑑登録証明書、リサイクル券、身分証明書
・小型特殊自動車の場合
委任状、印鑑登録証明書、リサイクル券、身分証明書、販売証明書、譲渡証明書
他にも、名義が異なる場合や未成年の場合によっても必要な書類が異なりますので、事前に調べておきましょう。
重機の引き取り
契約が成立すれば最後は重機の引き取りとなります。引き取りのタイミングで買い取り額のお支払いになります。しかし、業者によってお支払い方法やタイミングが異なるので契約時に確認しておきましょう。高く買取ってもらうための2つのコツ
重機の買取はコツをおさえることで高額な買取も期待できます。ここでは、押さえておくべき点について紹介します。

1. 洗車で綺麗にしておく
現物確認の前に洗車しておきましょう。重機本体の傷、汚れ、錆なども査定の対象になるため、事前に洗車しておくことで査定額が上がることがあります。
大切に使ってきたことのアピールにもなるので、買取業者の印象もよくなることでしょう。
2. 複数の買取業者で相見積もりをする
買取業者によっては得意とする重機が異なるので、買取価格に多少違いができます。複数の業者で相見積もりを行うと価格競争させることができるので、買取価格を吊り上げることが可能です。
しかし、何社も見積もりを取るのは面倒でしょう。
そのため、相見積もりはネットで行う一括査定がおすすめです。
一括査定は一度申し込んでしまえば、複数の見積もりが手に入るため、忙しい方でも手間と時間を掛けずに行えます。
重機の処分は買取を検討しよう
重機の処分は買取がおすすめです。
買取であれば無駄な費用を掛けずに、お金を貰いつつ処分することができます。
また、買取までの流れはそれほど難しくありません。手順を1つずつ確実に行えば簡単にできます。買取のコツを参考にして高値で売却しましょう。



 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


