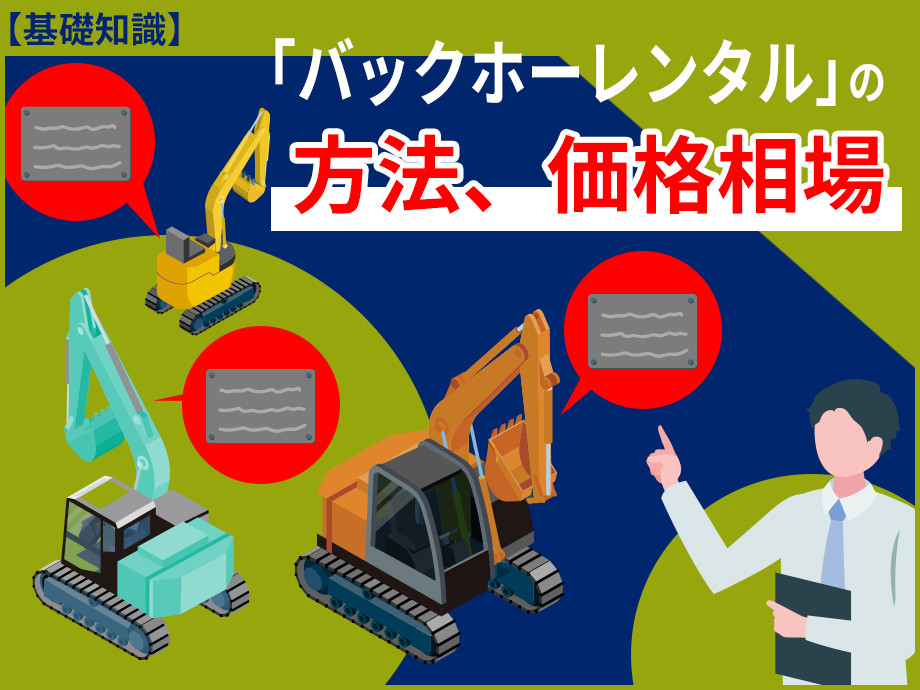
ユンボ
2025/04/15
29,353
バックホウのレンタルに必要な基礎知識!コンマ0.1(小型)、0.45(中型)、0.7(大型)クラスをピックアップして解説
【この記事でわかること】
- 後方小旋回などの仕様について
- 重量とコンマの見方
- レンタルの方法、価格相場について
ミニバックホウとは?使用用途について
ミニバックホウは、車体のコンパクトさを生かして、通常のバックホウでは困難な狭い場所での工事や造園作業、道路工事などに使用されています。また、農業用途でも活用されており、農道や排水路の整備、土壌の掘り起こし、植木の植え替え作業など多岐に渡る作業に使用されます。
ミニバックホウのメリット5つ
コンパクトかつ軽量で小回りが利く
また、車体が軽量のため、軟弱地盤でも沈み込みが少ないほか、土壌や舗装路への負担も少ないです。そのため、農作業や都市部での舗装工事などにもミニバックホウが向いています。小さい車体は、保管場所の確保もしやすく、農業や畜産業、造園での用途が広いミニバックホウは、高齢化が進む業界の人手不足を解消するツールとして役立っています。
個人でもメンテナンスがしやすい
また、小型機種であるため、消耗部品の交換価格も安く抑えられることが多いです。大型機種に比べて部品の入手性もよく、整備コストや維持費を大幅に削減できる点もメリットでしょう。
精密な作業が可能
後方小旋回、超小旋回で狭い場所での作業性が高い
また、超小旋回バックホウという機種もあり、こちらはアームの取り付け位置が運転席の横にあり、前後ともクローラーの幅からはみ出さずに旋回ができるものになります。しかし、アームの立ち上がりが高いため作業時は電線など頭上の障害物に注意が必要です。
小旋回機は形式に「U」と付くモデルが多いのでわかりやすいかと思います。例えば、コマツの場合は、小旋回機であることを表すため、形式に「UU」と表記されています。日立建機からは、ミニ超小旋回型(URシリーズ)がラインナップされており、超小旋回機には形式に「UR」という表記があります。
ミニバックホウを使用するユーザーは、市街地の土木工事、解体、林業など狭い現場が多く、旋回時は後方を気にせず安全作業ができるのが最大の利点です。
輸送が容易
バックホーの呼び方「コンマ」とは?バケット容量の選び方
しかし、バックホウについてある程度理解しているけど、その機種が何トンで何㎥掘削できるということまでは知らない、ということもあるかと思います。バックホウを選ぶ際は、基本的に車体の重量がとても大事になってきます。ここからは、初心者向けにバックホウの選び方について解説します。
バックホウの一般的な重さとバケット容量
一般的なバックホウのクラス・バケット容量
| クラス(重量t) | バケット容量(㎥) | コンマの呼び方 |
| 0.8t(800㎏) | 0.03㎥ | コンマゼロサン |
| 2t | 0.07㎥ | コンマゼロナナ |
| 3t | 0.1㎥ | コンマイチ |
| 4~5t | 0.2㎥ | コンマニ |
| 7t | 0.25㎥ | コンマニーゴ |
| 12~13t | 0.45㎥ | コンマヨンゴー |
| 20t | 0.7㎥ | コンマナナ |
| 22t | 0.8㎥ | コンマハチ |
※重量と㎥数はあくまで目安です。
このように、慣れてくるとバックホウの重量でコンマ(㎥数)を判断することができます。コンマは㎥数によってコンマイチ、コンマゼロサン…などの呼び方がありますが、初心者のうちはコンマのことは考えずに3t=0.1㎥、0.8t=0.03㎥と車体重量で覚えましょう。
バックホウの重量は形式の数字でも確認できる!
バックホウの重量を確認する際は、形式で判断するのも良いでしょう。
バックホウのクレーン作業は「最大吊上能力」を確認
従来のショベル作業に加え、クレーンによる吊り作業も可能なため1台2役をこなせる重機として土木現場などでは重宝されています。バックホウのクラスによって吊り上げできる荷物の重さが異なるので、現場でバックホウによる吊り作業を行う場合は、「最大吊上能力」の確認も忘れないようにしましょう。
バックホウは2トンクラスからクレーン機能付き機種が登場します。そのため、2トン未満のミニバックホウではクレーン機能付き機種がないため吊り作業ができません。
また、正式には移動式クレーンに分類されており、クレーン機能を使用するには「移動式クレーン」の資格が必要になるので注意してください。
バックホウのクラスごとの最大吊上能力
| バックホウのクラス(重量) | 最大吊上能力 |
| 2tクラス | 約400㎏ |
| 3tクラス | 約900㎏ |
| 4tクラス | 約1100㎏ |
| 7tクラス | 約1700kg |
| 13t | 約2900kg |
| 20t | 約2900kg |
バックホウは7トンクラスから、サイズが大きくなり中型バックホウとして分類されます。7トンクラスのバックホウで吊上げできる荷物は1.7トンと、かなり重たい物でも吊ることができます。13トンクラスにもなれば大型機種に分類され、最大吊上能力も非常に高く、約2.9トンまで吊り上げが可能です。
20トンクラスも13トンクラスも最大吊上能力は同じ2.9トンですが、これは法令が大きく関わっています。3トン以上の移動式クレーンは特定機種になるため、製造許可や検査がかなり厳しいものとなります。そのため、メーカーはあえて最大吊上能力は2.9トンに抑えているという事情があります。
ミニバックホウは寸法(サイズ)も大切
また、作業現場までミニバックホウをトラックなどの車両で運搬する際は、荷台の寸法、最大積載量に収まる機種を選択する必要もあります。特にトラックなどに最大積載量を上回る貨物を載せて走行した場合、過積載となり道路交通違反となるので機種選びは慎重に行いましょう。
バックホウの仕様・機能を見る
便利なクローラーの広幅機構
ブームスイングが可能なオフセットブーム仕様
排ガス規制・低騒音に対応しているか
排出ガス規制に対応している機種の場合は、機体に基準適合表示のラベルが貼られています。平成18年10月以降に製造・販売され、基準をクリアしているミニバックホウを使用することが法律で定められていて、規制開始前に製造された建設機械については規制対象外です。
近年のミニバックホウには、排ガス規制に対応した低燃費、低排出、低騒音の高性能クリーンエンジンが搭載されています。環境負担がより少ない機種は、燃費削減に貢献できるほか、住宅街や都市部の工事における騒音問題を解決します。
コンマ0.1(コンマイチ)クラス…小型軽量のミニバックホウ
ミニバックホウは操作パネルもシンプルで、トラックでの運送も容易なため初心者でも扱いやすい機種となって個人所有のハードルも低いです。注意点として、車体が小さいのでアームを少し動かすと衝撃でかなり揺れます。固定の場所で作業するブレード(排土板)を下して作業すると安定します。
車体価格も中古の場合は平均で¥1,000,000〜¥1,600,000程度で販売されているので、車体のほかバケット容量も小さいため、狭い場所での作業や農作業といったニーズで需要が高いです。しかし、除雪時は標準バケットでは効率が悪いため、降雪地は幅広バケットを用意するのをおすすめします。
コンマ1の主な機種はコマツPC30、日立ZX30 、ヤンマーVio20シリーズ、クボタRX3系などがあります。
コンマ0.45(コンマヨンゴー)…オーソドックスな中型クラスのバックホウ
主な機種としてはコベルコSK135やコマツPC128、住友SH125、SH135などがありますが、SK135は車両総重量が13800㎏もあるため、ほぼ14トンクラスと言っても差支えないでしょう。建設現場では一般的に13トンクラスバックホウのことをコンマヨンゴー(0.45㎥)と呼ぶことが多いですが、基準は組織や業種、世代によって異なるので注意してください。
コンマ0.8(コンマハチ)…大規模工事に導入される大型バックホウ
主な機種としてコマツPC200、PC228、コベルコSK225、SK200、住友SH200、SH235などがあります。コベルコSK225は後方小旋回仕様機種で、大きな建物の解体現場などに向いている機種と言えます。
バックホウのレンタルについて
バックホウをレンタルする際は、掘削、解体などの作業内容や使用するアタッチメントによって資格区分が異なるため注意してください。例えば、解体作業では車両系建設機械(解体用)の運転技能講習が必要です。
レンタル価格
小型バックホウ(1~3トン程度)
- 1日あたり:約¥10,000~¥40,000
- 1週間あたり:約¥50,000~¥80,000
- 1ヵ月あたり:約¥150,000~¥250,000
- 1日あたり:約¥15,000~¥25,000
- 1週間あたり:約¥80,000~¥120,000
- 1ヵ月あたり:約¥250,000~¥400,000
- 1日あたり:約¥25,000~¥40,000
- 1週間あたり:約¥120,000~¥200,000
- 1ヵ月あたり:約¥400,000~¥700,000
バックホウをレンタルする際は、掘削、解体などの作業内容や使用するアタッチメントによって資格区分が異なるため注意してください。例えば、解体作業では車両系建設機械(解体用)の運転技能講習が必要です。
レンタル価格
小型バックホウ(1~3トン程度)
- 1日あたり:約¥10,000~¥40,000
- 1週間あたり:約¥50,000~¥80,000
- 1ヵ月あたり:約¥150,000~¥250,000
- 1日あたり:約¥15,000~¥25,000
- 1週間あたり:約¥80,000~¥120,000
- 1ヵ月あたり:約¥250,000~¥400,000
- 1日あたり:約¥25,000~¥40,000
- 1週間あたり:約¥120,000~¥200,000
- 1ヵ月あたり:約¥400,000~¥700,000
- アタッチメント(例:ブレーカー、グラップルなど)使用の場合、追加で約¥1,000〜¥10,000/日程度。
- 輸送費:レンタル業者によっては現場までの運搬費が別途必要で、距離によりますが片道¥10,000〜¥30,000円程度が一般的です。
価格を決定する要因として、地域、レンタル期間、機種や装備の新しさがあります。都市部では価格がやや高め、地域では低めになる傾向があり、長期レンタルでは割引が適用されることが多いです。レンタル機種は各業者によって新旧さまざまなモデルがありますが、最新型や特殊装備を備えたモデルは、レンタル価格も当然高額になります。
具体的な価格は地元のレンタル業者に問い合わせるとより正確です。人気の業者には「アクティオ」「カナモト」「ニッケンレンタル」などがあります。


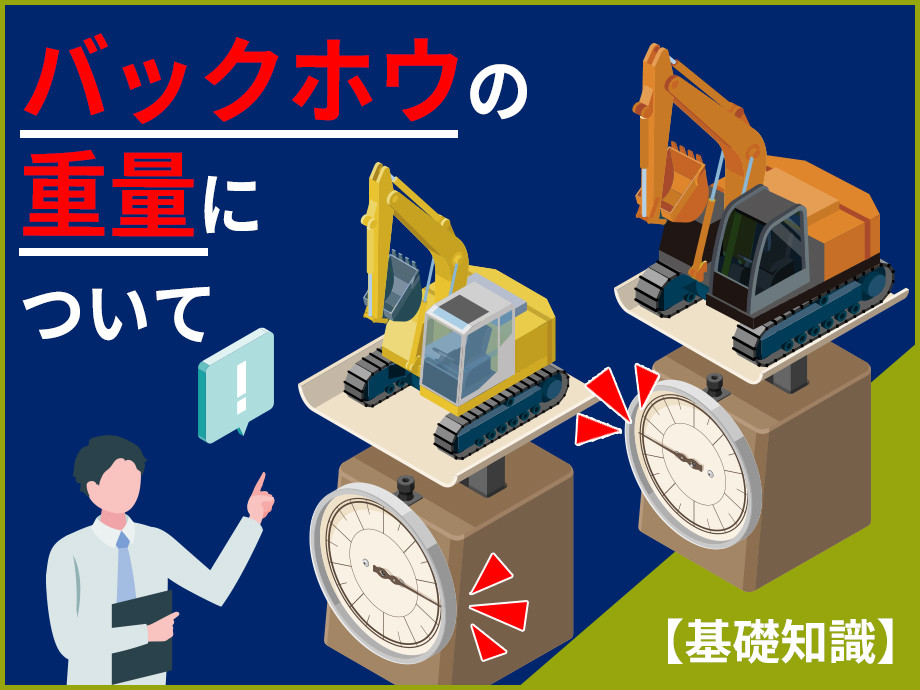
 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


