
ユンボ
2022/04/21
67,234
【意外と知らない】ユンボ・バックホー・ショベルカーの違いとは
-
目次
- 教本上の正式名称はバックホーまたはドラグショベル。それぞれの由来とは。
- 各名称の使い分け
- 土木現場での呼び名はバックホー。職業によって呼称が違う?
【ユンボ・バックホー・ショベルカー】の違いを解説

人によってはユンボ、バックホー、ショベルカーと色々な名前で呼ばれています。
主に掘削や整地作業などの工事現場で見かけることも多く知名度の高い建設機械ですが、どうしてこのように様々な呼び方があるのでしょうか?
このような疑問を抱く方も少なくないと思います。
結論を述べますと違いはありません。
では、それぞれの違いや実際の作業現場での呼び方についても併せて解説していきます。
教本上の正式名称はバックホーまたはドラグショベル。それぞれの由来とは。
小型車両系建設機械の講習テキストでは正式名称はドラグショベル又はバックホーと明記されていました。
ドラグショベル(バックホー)はものを手前に引き寄せる作業をする建設機械のことをそう呼んでいたことが由来になっているそうです。
特に耳にすることが多いのがユンボという言葉だと思います。
ユンボとは元々はフランスのシカム(SICAM)社の製品呼称名「yumbo」のことで、日本では登録商品名がそのまま使われたのが由来です。
車両積載形トラッククレーンがユニック車(ユニック:古川ユニック株式会社の商標)という名称で広く普及しているのと同じパターンですね。
また、ユンボと呼ばれるようになった理由の一つとして三行広告の求人欄で「ユンボオペ募集」など、ユンボという名称が多く使われたことが挙げられます。
ちなみに、小型のミニ油圧ショベルはミニユンボという呼ばれ方が一般的にされています。
そしてショベルカーとも呼ばれる由来についてですが、そもそもショベルというのは油圧ショベルという名前からわかるように、標準装備であるショベル(バスケット)(主に土砂を掘削するためのアタッチメント)のことです。
「土木工事に使う掘削用の動力シャベルを備えた車両全般」をさす和製英語としてショベルカーという呼び方が普及したそうです。
各名称の使い分け
| 油圧ショベル | 社団法人日本建設機械工業会またはJISでの統一名称。 |
| ショベルカー | 和製英語から普及した名称。メディアで使用される呼称。 |
| ドラグショベル(バックホー) | 国土交通省、官庁の文書にて表記される名称。 |
| パワーショベル | 小松製作所の商品名。 |
| ショベルカー | 報道などメディアでよく使用される呼称 |
| ユンボ | シカム社の製品呼称。 |
この表のように区分して考えれば整理がしやすいと思います。
J I Sというのは日本産業規格のことで国家標準の一つです。
つまり日本で正式登録されている統一名称は油圧ショベルで、国土交通省をはじめとした行政で使用される名称はドラグショベル(バックホー)ということですね。
ショベルカーは一般的に誰でもわかりやすい呼び方のため、テレビニュースや新聞のメディアで主に使用されている印象です。
どれも同じ油圧ショベルのことを指すと説明しましたが、ショベルの種類やアタッチメント、現場用途により呼び名が変わることが多いので使い分けには気をつけてください。
土木現場での呼び名はバックホー。職業によって呼称が違う?
これはその会社や地域にもよると思いますが、ブルドーザーを「ブル」、転圧機(ランマー)を「うさぎ」、手押しの一輪車を「ネコ」と呼ぶように、慣れ親しんだ「ユンボ」で呼ぶ作業員も少なくありません。
特にご年配のベテランや親方さんなどにそういう方が多いので、入社したての新入りはかなり混乱します。
また、公共工事の受注が多い会社ですと行政用語であるバックホーと呼ぶ人が殆どという印象です。
油圧ショベルを操作するのに受講が必要な特別講習や技能講習がありますが、名称はバックホーで教育しているのでその呼び方が普及している可能性も考えられるでしょう。
工事現場に民家が隣接している場合は、着工前(工事を始める前)に近隣住民へご挨拶をします。
騒音でご迷惑をお掛けする恐れがあることや工事期間、内容をお伝えするのですが、がその際、バックホーや油圧ショベルでは相手にも伝わらないので、わかりやすいように「ショベルカー」と説明をすることもあります。

ユンボ・バックホー・ショベルカーの違い|まとめ
掩体壕や塹壕などの防御陣地を構成するのに活躍しますが、全ての隊員はシンプルに「油圧」という呼び方で統制されていました。
使用現場での重機の呼び方は会社や組織、受けている仕事の種類によって異なる場合があるというのが結論でしょう。

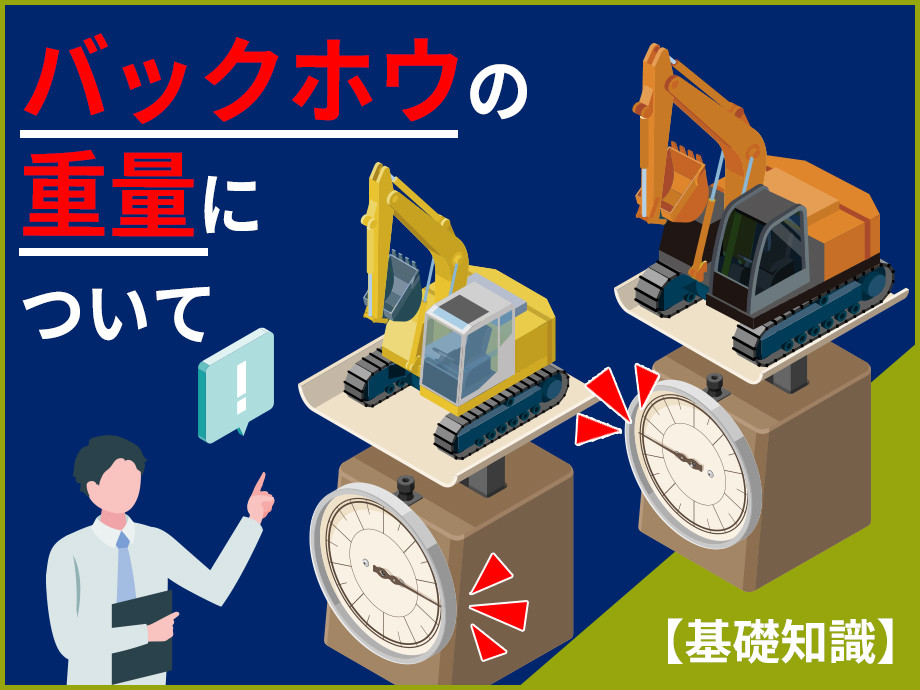

 Facebook
Facebook Instagram
Instagram TikTok
TikTok


